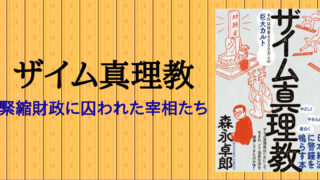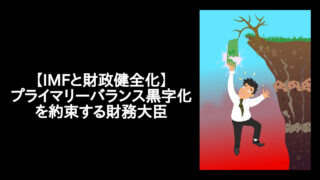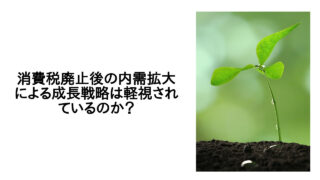防衛費の財源はあるのになぜ消費税廃止の財源はないのか?
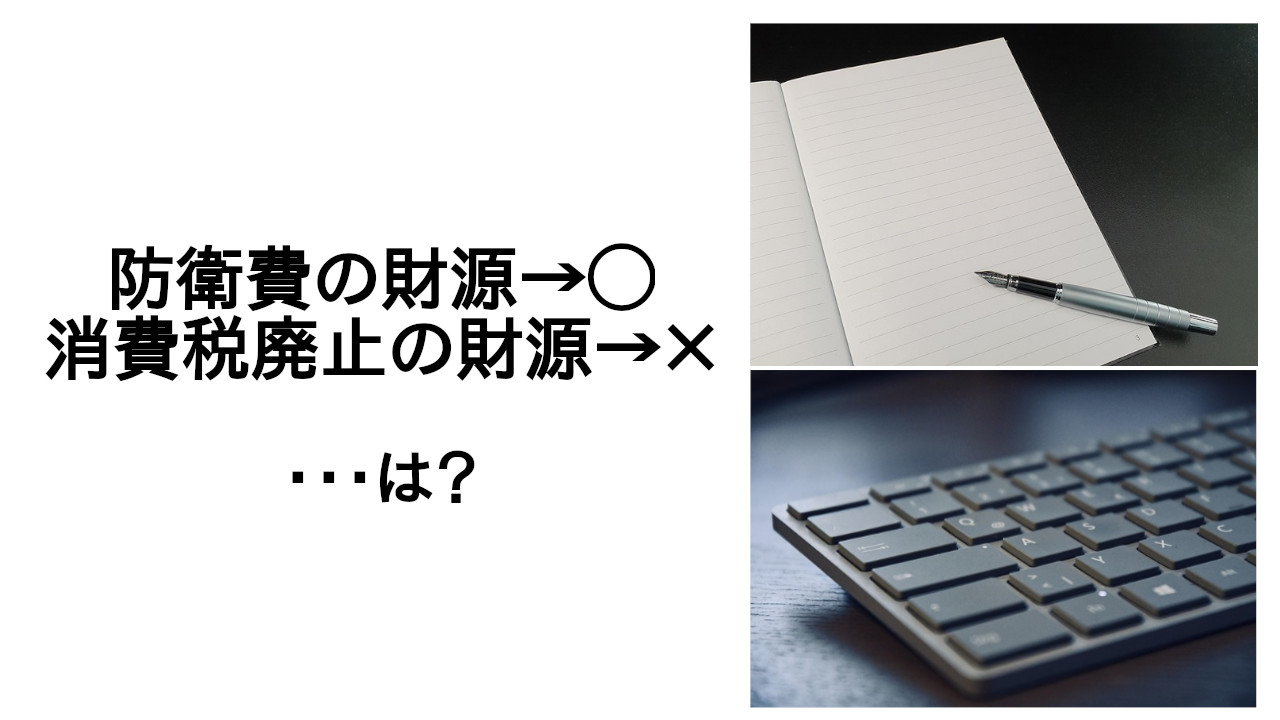
防衛費の増額には財源を無視してバンバン財政出動するのに、なぜ消費税の廃止には財源がないとか、足りないとか言うのだろうか。
このような疑問は日本の財政政策や政治的意思決定の矛盾を鋭く突いたものだ。この点について現状の財政行動、政府の優先順位、政治的背景を踏まえて考えてみたい。
個人的には「財源」という言葉は使いたくないのだが、失われた30年で時が止まったままなのか情報がアップデートされない方々がまだまだいるようで、当サイトでは便宜上、この言葉を用いている。
防衛費増額と財源の現実
防衛費の状況
防衛費の規模
2022年12月の安保三文書改定で政府は、2023〜2027年度の5年間で総額43兆円(年平均8.6兆円)の防衛費を計画。2025年度単年では約8〜10兆円に達する見込みだ。
従来の予算
防衛費は長らくGDP比1%(約5〜6兆円)だったが、NATO基準GDP2%に近づける方針で倍増。
財源の扱い
当初、政府は「増税」で賄うと表明。具体的には、「法人税や所得税」、「たばこ税の増税」で約1兆円を確保する案が出たが、残りは国債発行や既存予算の組み替えで対応している。
財源無視の実態
国債依存
2023年度予算では防衛費増額の大部分(約3〜4兆円)が新規国債で賄われた。財務省は「当面は国債で対応し、後で増税」という説明だった。
予算の柔軟性
防衛費に関しては、一般会計の予備費や補正予算を活用し、「財源確保は後回し」という姿勢が目立つ。
2024年度補正予算でも防衛関連に数兆円が計上され、国債発行が前提である。
政治的優先度
ロシア・ウクライナ戦争や中国の軍事圧力を受け、防衛費は「待ったなし」と位置づけられ、財源の裏付けよりもスピードが重視されている。
消費税廃止と財源の違い
消費税廃止の規模
消費税収は2023年が約23兆円。2024年度は約23兆8千億円で過去最高を更新。
対して、防衛費増額は年3〜4兆円(5年で43兆円)で、消費税廃止の財政インパクト(23兆円/年)に比べれば小さい、というのがザイム教徒と大日本帝国の亡霊たちの主張である。
財源の扱いの違い
防衛費増額
防衛費は「緊急性」を理由に国債発行や予算のやりくりで対応。政府は「将来の増税」で帳尻りを合わせると主張するが、具体的な実効は先送りである。
消費税廃止
永続的な歳入減(23兆円/年)となり、国債で埋め続けるのは財政規律困難。防衛費のような「一時的支出」と異なり、構造的な穴が開くため財政確保が必須とされる、とザイム教は主張する。
財政規律のダブルスタンダード
防衛費
安全保障は国の根幹とされ、国債増発が許容される。政治的コンセンサス(特に与党や米国から圧力)もあり、財源ガーたちの批判が抑えられている。
消費税廃止
国民生活への影響は大きいが財政健全化が優先とされ、なぜかこちらは財源確保が前提となっている。財務省や経済界が強く抵抗し、政治的ハードルが跳ね上がる。
なぜ「財源がない」と言われるのか?
財政の持続性
国債依存の限界
日本の公的債務はGDP比200%超(約1200兆)。防衛費の数兆円は誤差の範囲でも、消費税収23兆円は金利上昇や国債暴落のリスクがある、というのがザイムおよび大日本帝国の亡霊の主張である。
利払いの負担
国債が増えると利払い費が膨張する(2025年度で約10兆円)。消費税廃止で毎年23兆円の赤字が加われば、財政破綻へのカウントダウンが加速するとザイム教は考えているようだ。
政治的優先順位
防衛費
国際情勢や米国との同盟強化が後押しして、やらざるを得ないと政府が判断。さらに、中国脅威論を真に受けた一部のネトウヨや戦火を夢見る大日本帝国の亡霊どものネット上での不安を煽るムーブが追い風か。
消費税廃止
多くの国民の支持はあっても、大企業(輸出還付金)と財務省(財政健全化)、与党(安定財源確保依存症)の三位一体の、もはや宗教的ともいえる障壁に阻まれている現在である。
経済界の影響
防衛費
防衛産業(三菱重工)や輸出企業がさらなる恩恵を受けるため、経済界は黙認。
消費税廃止
消費税廃止により輸出還付金(補助金)が無くなる輸出大企業や、法人税増税を恐れる企業が猛反発するだけでなく、経団連などのロビー活動や企業献金が消費税廃止を阻む。
「バンバン財政出動」と「財源がない」の矛盾
昨今、ネット上でも多くの人が主張しているとおり、防衛費増額で「財源を無視」しているのに、消費税廃止には「財源がない」というのはダブルスタンダードにしか見えない。
その背景には次のことが影響していると推察される。
短期 VS 長期
防衛費は「一時的な危機対応」と位置づけられ、国債で凌げる。一方、消費税廃止は「永続的な歳入減」で国債頼みが持続不可能、というのがザイムおよび大日本帝国の亡霊たちの主張だ。
政治的な都合
防衛費は政府の威信や国際公約に関わるが、消費税廃止は国民へのバラマキと見なされ、教義である財政規律が許さない。
国民への説明
防衛費は「国防のため」と正当化しやすいが、消費税廃止は「財政破綻のリスク」があると脅され、「税は財源・国民の借金・日本は借金大国」といった長年におよぶプロパガンダで洗脳されている国民もまだまだ多く、これまでは支持が集まりにくかった。
日本はどうなる?
このような矛盾が続けば、人々の懸念「日本が滅びる」につながるリスクは確かにあるだろう。
国債依存の加速
防衛費で国債を増やしつつ、消費税を維持する構造は永続的な国民負担の増大を意味する。
経済の疲弊
消費税で内需が圧迫され、防衛費で企業優遇が進めば、さらに格差が拡大され、経済停滞が続き、日本の経済再生が遠のく。
国民の不信
すでに崩れだしているが、「防衛費には金を使うのに、国民の負担軽減は後回し」と国民が感じれば、政府への信頼が崩壊する。
解決への提案
防衛費の見直し
43兆円のすべてが必要か精査し、無駄を削減。財源を消費税廃止に振り向ける。
国債の優先順位についての議論
防衛より国民生活(消費税減税・廃止・社会保障の減免・全世帯への給付金など)に国債を使う選択肢を議論する空気をネットや市民の生活レベルにおいても醸成していく。
国民からの政治的圧力
ネット世論や選挙、デモなどで「防衛費よりも消費税廃止を!」と声をあげ、国民の声により政府に優先順位の変更(国債の使いみちを国民生活優先にする)を迫る。
結論
防衛費増額に「財源無視」が許されるのは、年に数兆円と規模が小さく、国防という政治的な優先度が高いから。
一方、消費税廃止は「年に23兆円」と規模が大きく、財政構造を揺るがす可能性があるため、「財源がない」や「財源どうするの?」といった財源ガーのお決まりのセリフで騒ぎ立てる。本来であれば、経済も農業も国防だろうに。
このダブルスタンダードは政府の都合と経済界の影響が大きい。
これを不公平だと感じるなら、防衛費の国債依存を批判しつつ、幾つもの消費税廃止のための財源を具体化(国債発行・輸出還付金の廃止・所得税の累進課税強化・法人税率の見直し・金融所得課税の増税・中抜き省庁の解体など)する議論を活発化させるのが一案である。そして時は動き出す。
関連記事