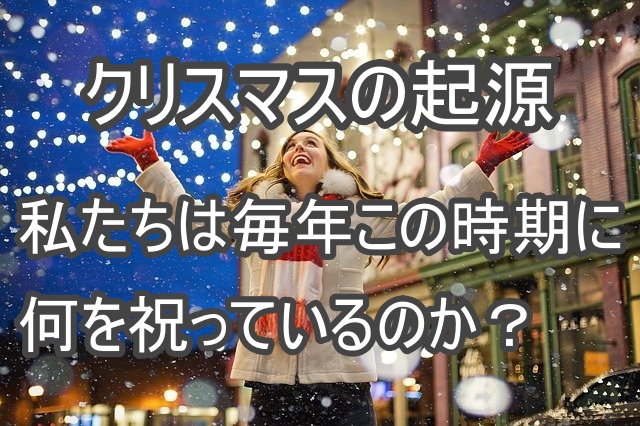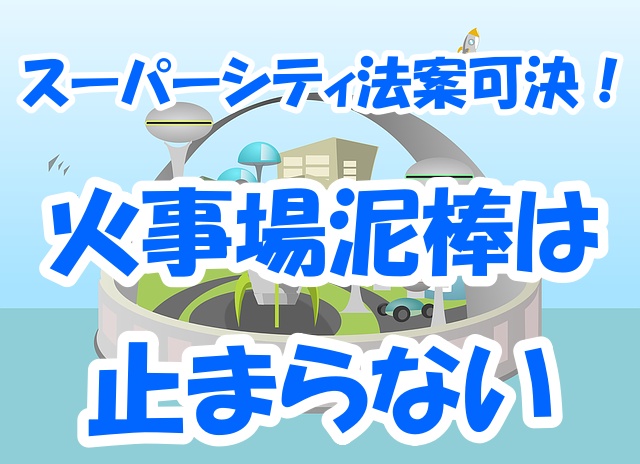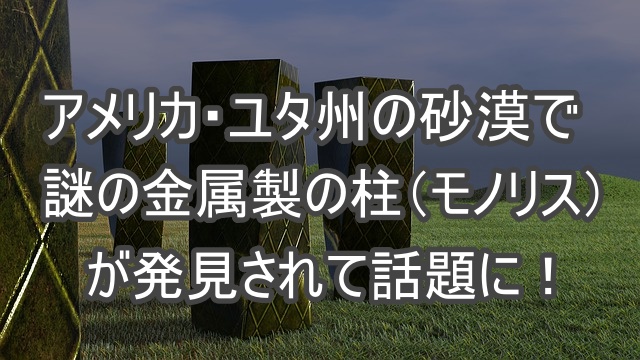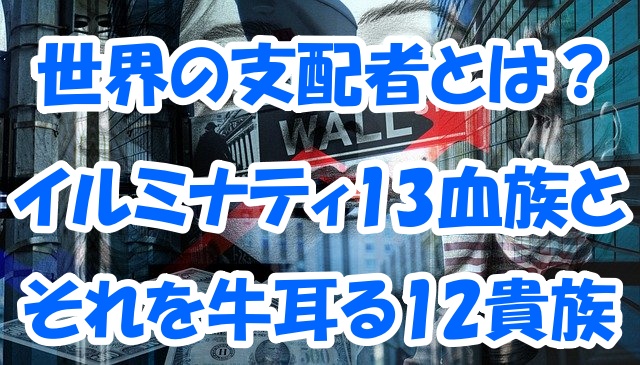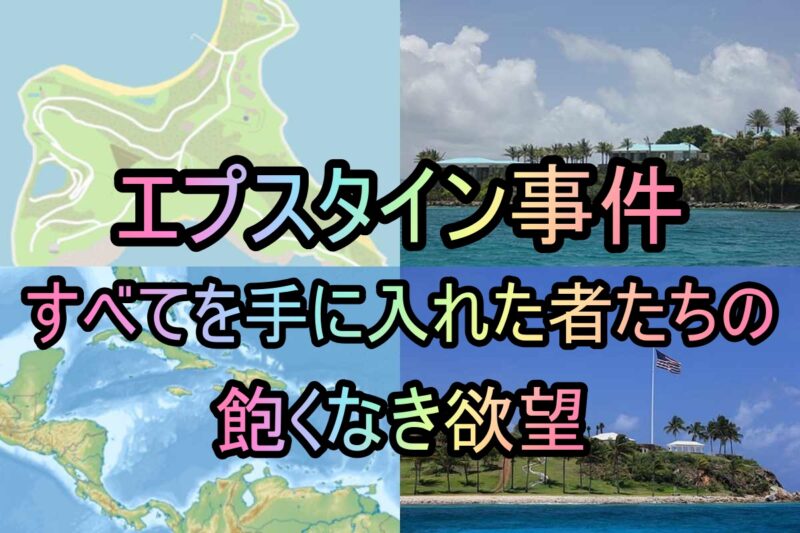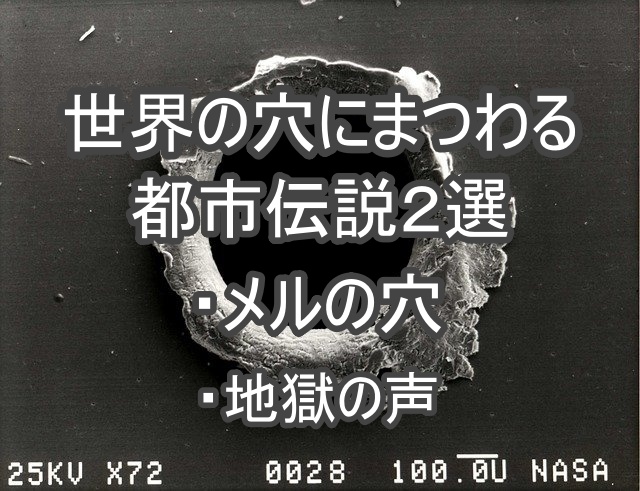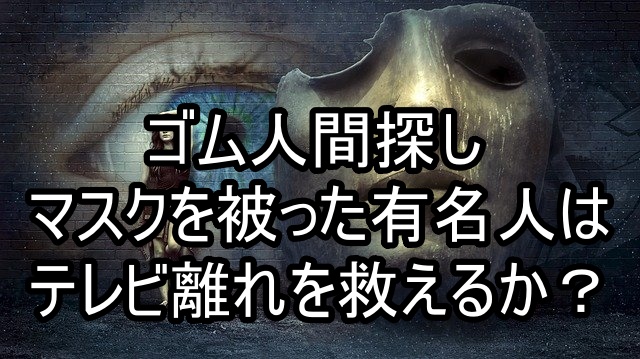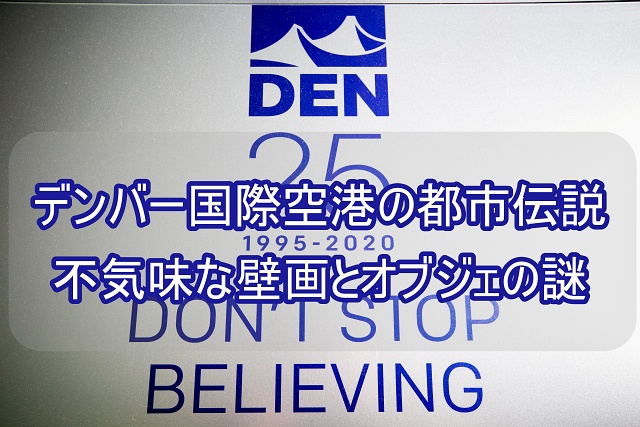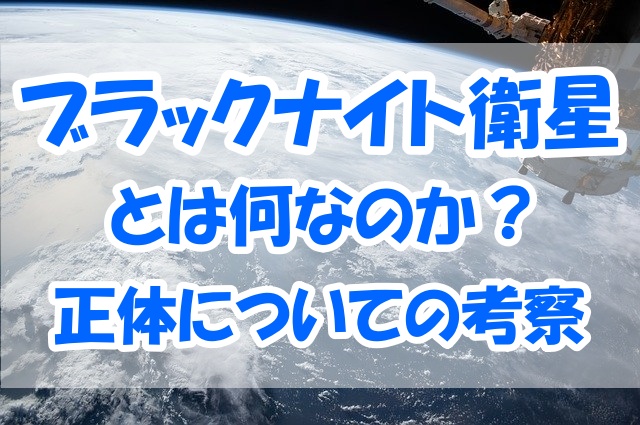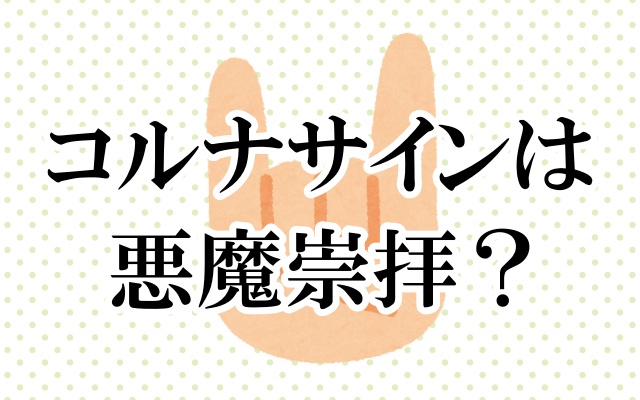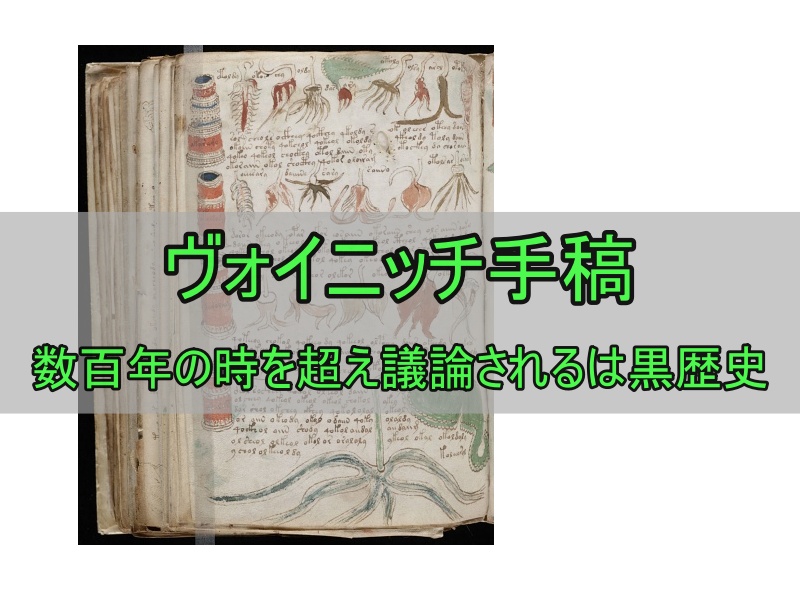サタンの礼拝組織であるイルミナティは昔から祝祭日を改ざんし、大衆をコントロールしてきたのだろうか。
そして、異教徒の祭典を維持し、大衆は無知のまま彼らの伝統であるオカルト儀式に参加させられているのだろうか。
そして、クリスマスに登場するサンタ・クロースの正体についても諸説あるようだ。
- サンタクロースの正体について。
サンタクロースの正体
サンタクロースの正体については次のような説がある。
- 聖ニコラウス説(シンタークラウス)
- 北欧神話の神オーディン説
①聖ニコラウス説
1つ目は、サンタクロースの正体は「シンタークラウス」であるとする説。
シンタークラウスのモデルはキリスト教の聖人「ニコラウス」ではないかと言われている。
また、「靴下にプレゼントを入れる」という話も聖ニコラウスのエピソードから来ているようだ。
サンタクロースのモデルはシンタクラースである。そのシンタクラースのモデルは「ミラのニコラオス」ではないかと言われている。
「ミラのニコラオス」も参照4世紀頃の東ローマ帝国・小アジアのミラの司教(主教)、教父聖ニコラオス(ニコラウス)の伝説が起源である。「ニコラオス」の名はギリシア語表記。ラテン語ではニコラウス。イタリア語、スペイン語、フランス語ではサン・ニコラ。イタリア語ではニコラオとも。ロシア語ではニコライ。
以下のような伝説のほか、右に挙げる絵画のように無実の罪に問われた死刑囚を救った聖伝も伝えられている。
「ある時ニコラウスは、貧しさのあまり三人の娘を身売りしなければならなくなる家族の存在を知った。ニコラウスは真夜中にその家を訪れ、窓から金貨を投げ入れた。このとき暖炉には靴下が下げられていており、金貨はその靴下の中に入ったという。この金貨のおかげで家族は娘の身売りを避けられた」という逸話が残されている。この逸話が由来となり、「夜中に家に入って、靴下の中にプレゼントを入れる」という、今日におけるサンタクロースの伝承が生まれている。また、ニコラウスの遺骸はイタリア南部の都市であるバーリに移されたとも言われている。
出典:ウィキペディア
サンタの使い魔クランプス
サンタ(聖ニコラウス)に付き添っているのはトナカイだけではない。サンタの背後には悪魔の手下がいる。それが、使い魔のクランプス(KRAMPUS/SANTA’S ELVES)だ。
クランプスは精霊と言われているが、悪の遣いとして聖人ニコラウスに付き添う。聖人ニコラウス(サンタ)は良い子にはプレゼントを与え、悪い子にはクランプスを使って子供達にお仕置きをするという。
クランプスは「悪魔」と「山羊」を組み合わせたもので「悪」や「罪」のシンボルという見方をする人もいる。聖書に登場する「ヨム・キプル」という祭日には祭司が、聖なる場所に入り1年の奉納として生贄の山羊2匹を捧げていた。
- 匹目の山羊は「ラ・アドナイ」といって神「ヤハウェ」に捧げられる
- 匹目は「ラ・アザゼル」といい、荒野に連れていかれ崖から落とされる
ラ・アザゼルの山羊には大司祭の手が置かれる。その手には人間全ての罪が集約されており、山羊の頭にその罪を注入するという意味があった。
古代神話に登場するアザゼルは全ての罪を背負わされたともいえる。
現代でも「身代わり」や「生贄」という意味でスケープ・ゴート(scapegoat)という言葉が使われるが、その言葉の由来も「贖罪の山羊」から来ている。
クランプスの正体はアザゼル
この伝統が現代のクリスマスに受け継がれ、サンタの付き添いが「アザゼル」となり名前は「クランプス」に変わった。こちらの映像では、祭りを通してクリスマスと聖ニコラウスの悪魔的な側面を賛美しているようにも見える。
聖ニコラウスと使い魔クランプスは、現在でもオーストリア、ハンガリー、ドイツ、イタリアなどのヨーロッパ各地のクリスマスに登場し祀られている。
神話に出てくるゴブリンや日本の行事である「なまはげ」の鬼にも似ているなと思ったのだが、どうだろうか。この儀式は日本のクリスマスとも違っており、不気味である。
ジングル・ベルの由来
また、学者たちは「ジングル・ベル」の由来も指摘しており、これはクランプスが身に付けていた「ベル」が由来なのではとされている。
クランプスは、『ジングル・ベル』の曲が作られる前からベルを付けていたという。
首に吊るされたベルを鳴らして、自分たちの存在を示し、これから向かう村への合図にしていたので、クリスマスベルやジングルベルはそうした慣習から来ていると信じられている。
現代サンタの赤い服はコカ・コーラの陰謀?
18世紀になるとオランダ人がアメリカに移住した際に「シンタークラウス」を持ち込んだ。この時に呼び方が訛って「サンタ・クロース」になった。
1930年、コカ・コーラ社のデザイナーが冬季の販売戦略を考える。その内容はシンタークラウスにコカ・コーラのカラーである赤と白を取り入れ、もともとの設定にトナカイを追加したことで現代版のサンタクロースが生まれた。
その後、この格好をしたサンタが徐々にグローバルスタンダードになっていったともいえる。
②北欧神話の神オーディン説

北欧神話には「オーディン」という神がいて、この神がサンタクロースの正体だとする説もある。
オーディンは多種多様な概念を持つ神で、次のことを司るとされる主神である。日本のアニメやテレビゲームに登場することもあるのでご存知の方も多いだろう。
- 戦争
- 死
- 肉欲
- 酒
- 知恵
- 魔法
- オカルトの知識
- 呪文
- 詩文
北欧民族は、太陽神と同時に神話の神オーディンを信奉していた。
「クリスマスの起源」についての記事でも書いた「サートゥルナーリア祭」を行う異教徒の考え方とオーディンが内包する概念には共通するものがあったため、神話の神オーディンは一躍人気の神となった。
そして、オーディンは太陽神(バアル)と同等とされ、この神はのちにサンタ・クロースのモデルになったと言われいる。
サンタクロースとイエス・キリストの共通点
ヨシュア(ヘブライ語: יְהוֹשֻׁעַ, Yehoshuʿa)は『旧約聖書』の「民数記」や「ヨシュア記」に登場するユダヤ人の指導者。新約聖書のイエスと同じ名前。יהוה(ヤハウェ/ヤフア)は救いという意味。
(出典:ウィキペディア)
サンタクロース(オーディン)はイエス(ヨシュア)によく似ている。
イエス・キリスト(ヨシュア)という言葉は「救済」を意味する。
北欧神話の神・オーディンも「救済者」として描写されており、本物の救世主にそっくりなのだ。
北欧神話の神オーディンの特徴
サンタクロースの正体を知るには、オーディンの特徴を知る必要がある。
オーディンの特徴は以下のとおり。
- 背の高い老人
- 白く長い髪を生やしている
- 司教杖(しきょうじょう)という杖を持っている
背の高い老人で白い髭を生やしているというのは、まんまサンタクロースの特徴でもある。
また、司教杖とはカトリック教会の司教が祭事の際に持つもので、杖の上部が蛇の形をしているため別名「蛇の杖」とも呼ばれている。
エデンの園でイブに嘘ついて、そそのかした蛇は悪魔の象徴である。そして、神オーディンも蛇に姿を変えることがあったと神話では語られている。
トナカイのモデルはオーディンの軍馬スレイプニル

サンタの橇(ソリ)を引く「8頭トナカイ」の由来は、北欧神オーディンが乗っていた8本の足を持つ軍馬「スレイプニル」と言われている。
現在では、サンタのトナカイは9頭であるという話もあるが、これは1930年代に作られた赤鼻のトナカイ「ルドルフ」の童話から来ている。
あとがき
クリスマスの起源は異教徒のお祭りで悪魔崇拝という説がある。
サタン・クロースの起源が、聖ニコラウスでも北欧神話の神オーディンだとしても、その周囲には悪魔的なシンボルが散りばめられている。
案外、身近にある年間行事やイベントの裏側には私たちの知らない何かが巧妙に隠されているのかも知れない。
クリスマスの起源