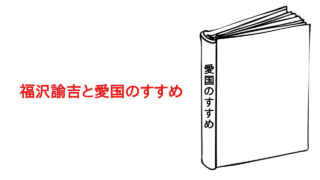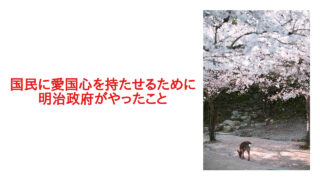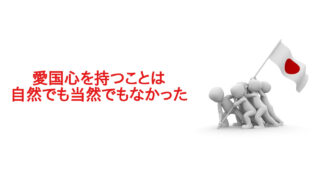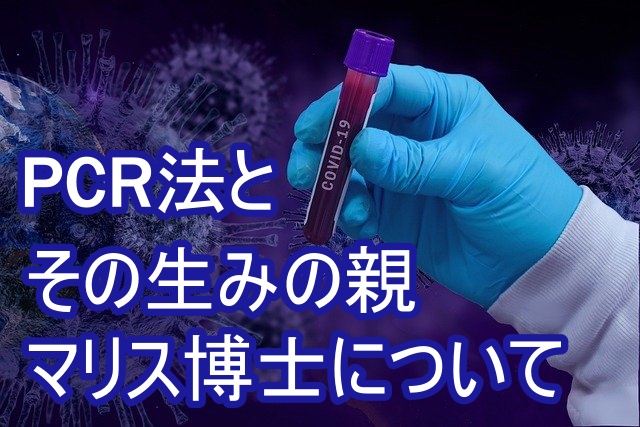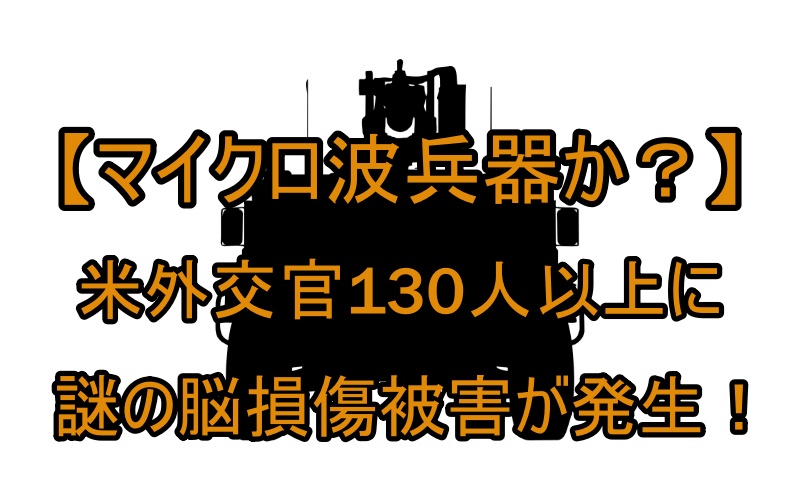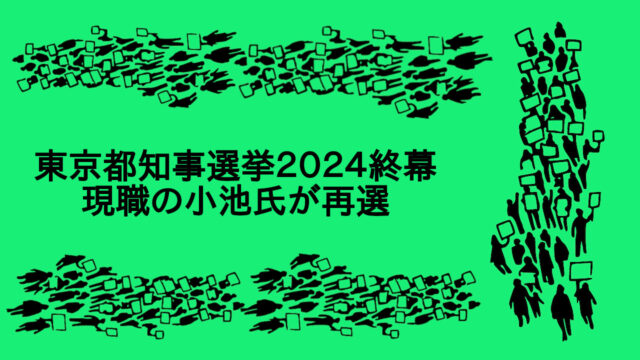愛国の起源はパトリオティズム
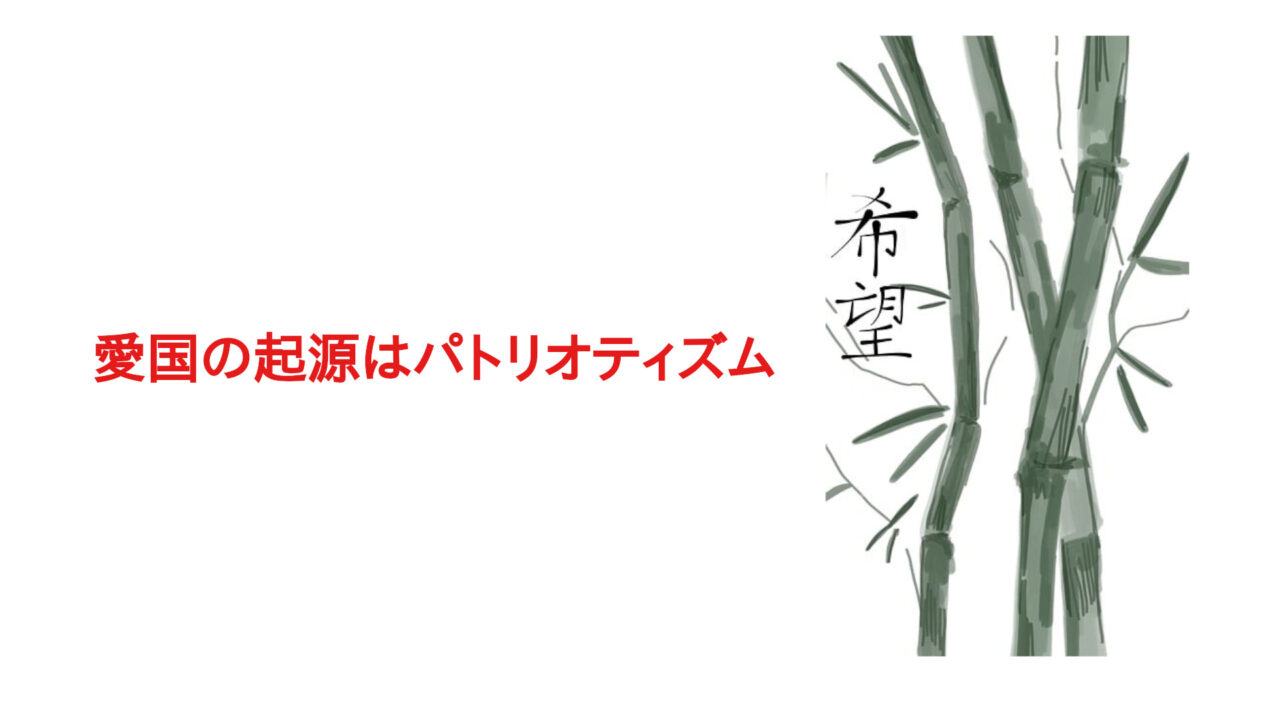
そもそも「愛国」という思想の歴史は古代ギリシャやローマまで遡ることができる。18世紀末までは、我々が保守とか右派とか呼んでいる政治的イメージとはあまり関係がなかった。
この「愛国」という思想が保守や右派などの政治的立場と結びついたのは歴史的には比較的最近のこと。愛国については、後付けの刷り込みや先入観のせいでその総体が見えなくなっていることが多い。
ここでは18世紀末までの愛国思想とは、どのようなものだったのか。どうして「愛国」という概念が保守や右派の一部である、といったイメージが生まれたのかについて考えてみたい。
日本における愛国のイメージ
ヨーロッパ由来の本来の意味での愛国心とは、現在多くの日本人が愛国だと考えているものと大きく異なっている。
現代日本では「愛国」や「愛国心」という言葉のイメージから次のようなことが連想される。また、そのような意味で国を愛することが当然だと考える人も多い。
- 海外で日本人のスポーツ選手やアーティストなどが活躍している
- 富士山など日本の美しい自然景観を愛している
- 日本の職人のものづくりの伝統を愛している
- 茶道や華道といった日本独自の文化を愛している
- 古代から受け継がれてきた日本の素晴らしい歴史を愛している
その一方で「日本すごい・日本が好き・日本に生まれて良かった」という言葉をいちいち口に出さずにはいられない、わざとらしく、度を越した日本礼賛になんとも言えない気持ち悪さを感じたりもする。
また「愛国・愛国心」という言葉にアレルギー反応を示す人も多い。それは「愛国」という言葉のイメージが戦前や戦中の日本の「軍国主義」や「ナショナリズム」を想起させるからだ。
この場合の愛国には次のように排他的で右翼的なイメージがつきまとう。
- 侵略戦争
- 国旗や国家
- 外国人差別
日本では愛国心の対象として、この国の政治的価値や法制度を思い浮かべる人は、ほとんどいないが、ヨーロッパの伝統的な愛国心では日本人があまり思い浮かべることのない法的・政治的な価値を思い浮かべる。
愛国心という言葉は存在しなかった
そもそも「愛国心」という言葉は日本に存在しなかった。ところが古い日本の文献を見てみると、ごく稀に「愛国」という言葉が見つかる。
『日本書紀』には、大伴部博麻という兵士の逸話がある。この話は第二次世界大戦の頃、愛国心の模範として書籍で紹介されていた。
663年、博麻は「日本・百済」と「中国・唐」が戦った「白村江の戦い」に従軍し、唐軍の捕虜となった。彼は捕虜でいる間に唐軍の日本侵攻計画を知ることになる。
ところが、この情報を京都の朝廷に届けようとするも、日本に帰国する旅費がなかった。そこで博麻は自らすすんで奴隷となり、その代金を仲間の土師連富杼ら4人の豪族に渡して帰国させた。
こうして博麻は30年間、異国の地に留まったのちに帰国すると、持統天皇は次の言葉をかけ、多くの褒美を与えたという。
「富杼らは博麻そなたの計画に従い、日本へ帰ることができた。そなたはひとり他国に30年ものあいだ留まった。わたしはそなたが朝廷を尊び国を思い、奴隷に身を落としてまで忠誠を示したことがたまらなく嬉しいのだ」
持統天皇が博麻にかけた言葉の中に「国を思い」という表現が出てくるが、この言葉の原文こそが「愛国」だった。
日本史研究科の平田俊春氏によれば、明治4年以前に「愛国」という言葉が使われたのは中国語文献からの引用を除けば、上記の例を含めてわずか3例しかない。
愛国や愛国心という言葉が頻繁に使われだしたのは、明治に入ってからなのだ。
パトリオティズムとは
日本語の「愛国・愛国心」を英語で言うとパトリオティズム(patriotism)である。
明治の人々が「愛国」や「愛国心」について語るとき、それは欧米から輸入されたパトリオティズムという概念を意味していた。
パトリオティズムの語源はラテン語のパトリア(patria)という言葉に由来する。パトリアは「祖国」を意味する。祖国とは「先祖代々住んできた国」や「自分が生まれた国」のこと。
哲学者キケロと祖国
パトリアの歴史について遡れば、古代ローマの哲学者キケロにたどり着く。キケロによればパトリア(祖国)には2種類あるという。
- 自然的な祖国:生まれ故郷、生まれ育った場所への愛着
- 市民的な祖国:自分が市民権を持つ国
「自然的な祖国」が土地や自然環境、そこに住む人々を具体的に指すのとは対照的に、「市民的な祖国」は市民権を有するといった法的な共同体で抽象的な存在である。
キケロの場合は、生まれ故郷(郷土愛)よりも自分が市民権を有する国、共和政という政治形態が実践されていた市民的な祖国である「共和政ローマ」の方がはるかに重要だった。
キケロにとっての祖国とは、故郷の美しい景観や人々ではなく、共和主義の主張そのものだった。
共和主義と共通善
「市民的な祖国」にとって重要なキーワードは次の2つ。
- 共和主義:市民の自治を通じて共通善を守ることを重視する思想
- 共通善:自由や平等、多くの人々にとっての価値を実現する政治制度
共和主義とは、市民の自治を通じて市民にとっての共通善を守ることを重視する思想である。
共通善は、自由や平等、そしてそうした価値の実現を保証する政治制度。一部の者たちの私益のためではなく、多くの人々にとっての利益とされる政治的価値や制度のこと。
このような伝統から、ヨーロッパ諸国では愛国心とは共和政的な政治的価値や制度を防衛することにこだわる思想、政治的姿勢だと理解されてきた。
愛国心の敵は暴政
逆に、愛国心が敵と見做すのは、市民にとっての共通善を脅かす暴政だ。
暴政とは、一部の人々が私利私欲のために権力を乱用して、共通善を脅かすことで腐敗する政治の状態のこと。
たとえば、イタリア・ルネサンス期を代表するマキャベリのような思想家たちは、愛国心とは暴政に対抗するものであると理解していた。多くの場合、愛国者とは反体制派に属するものだった。
愛国心とは、暴政に対抗する政治的姿勢。多くの場合は反体制派に属するもの。
なぜなら、体制側こそが共通善のためではなく、私益のために権力を私物化し得る存在だからだ。
このようにヨーロッパの国々では、愛国心とは共通善(その国に住む多くの人々にとっての利益)を脅かす権力の乱用に抵抗する政治的な態度や姿勢を意味した。
愛国とは共通善に奉仕すること。
本来の愛国心とは、一部の人々の利益のために政治を私物化する権力者に抵抗する態度や姿勢のことなのだ。
あとがき
何者にも成れなかった自分の存在の軽さに耐えられず、それでもちっぽけでクソみたいなプライドやアイデンティティを保つためなのだろうか。
世の中には、自分の生活や人生が上手く行かないことの怒りの矛先を国内にいる外国人へ向け、これは差別ではなく区別だ、などと詭弁を使い、罵詈雑言を投げつける悪趣味な者たちがいる。
お国のためだと言い訳して自分より立場の弱い者や移民、外国人を排斥することを愛国心とは言わない。それは、この美しい日本にとっての恥部である。
関連記事