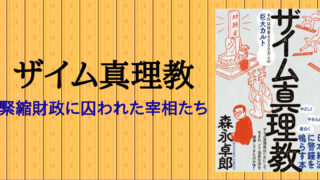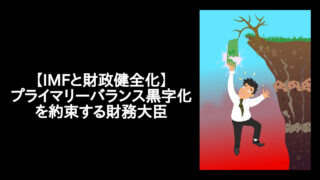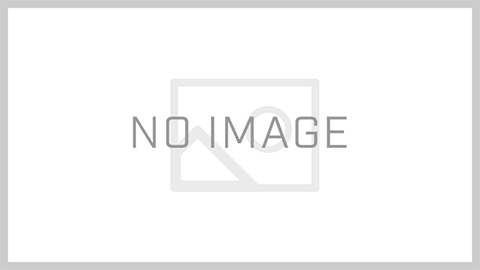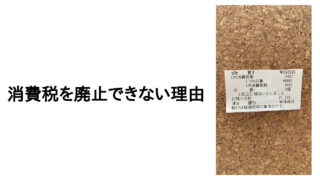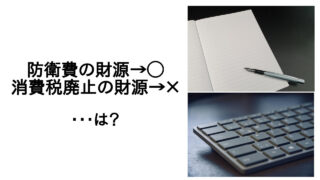どうすれば消費税廃止できるの?

どうすれば消費税は廃止できるのか?
まずは、法人税の税率を消費税導入前へ戻し、なおかつ大企業の輸出還付金を廃止すれば、消費税廃止は可能ではないのか。
消費税廃止を法人税率の引き上げ(消費税導入前の水準への回帰)と輸出還付金の廃止で実現するというアイデアは理論上では一つの実行可能なシナリオである。
提案(アイデア)の概要
- 消費税の廃止:2025年時点の消費税収は23兆円。これをゼロにする。
- 法人税率を消費税導入前(1989年以前)に戻す:当時の法人税基本税率は約40%。地方税も含む実効税率は50%超え。現在は約23.2%で実効税率は30%。
- 輸出還付金の廃止:年間4〜5兆円とされる大企業への輸出還付金をなくす。
法人税率を1989年以前に戻すと得られる効果
現状の法人税収
2023年度の法人税収(国税分)は、約14.5兆円、地方税も含むと約18兆円。現在の実効税率は約29.74%(国税23.2%+地方税)。
ちなみに、2024年度の一般会計税収約73兆円の内訳は次のようになっている。
- 法人税:約18兆1000億円
- 所得税:約20兆1000億円
- 消費税:約24兆3000億円
企業の所得税よりも低所得層が困る「逆進性」が強い消費税が最大の税収になっている。
税率を40%に戻した場合
1989年以前の法人税の基本税率40%(実効税率50%超)に戻すと、どうなるか。法人税収は税率に比例して増加すると単純計算できる。
- 税率23% → 14.5兆円
- 税率40% → 25兆円
- 実効税率50%超 → 30兆円
現在の税率23.2%で14.5兆円なので、税率が40%になると25兆円となる。地方税を含めた実効税率50%超とすると、総額で30兆円近くまで増える可能性がある。
法人税率を元に戻すと、現状の18兆円(国+地方)から30兆円へ約12兆円の増収。
企業の租税回避
税率が上がると、企業が海外移転(タックスヘイブン利用)を増やすリスクがあり、1989年よりもグローバル化が進んでいるので、税収が単純比例で増えない可能性もあるとされる。
しかし、総務省の調査によれば、企業が海外移転する理由の第1位は「消費需要を求めて」のことで、税制を理由とするのは少数であると報告されている。
だから、消費税の減税、廃止をおこない国内需要を喚起し、消費者の購買意欲を高め、企業の投資や労働者の賃金上昇を促進していこうと考えるのが積極財政派の主張である。
経済への影響
法人税増税は企業の投資意欲や賃金上昇を促し、GDP成長率にプラスに影響する可能性がある。これは税で持っていかれるくらいなら、設備投資や賃上げに使った方がいいと考えるからだ。
輸出還付金の廃止
還付金の規模
輸出還付金は年間約4〜5兆円(2023年ベース)。これを廃止すると、その分がそのまま国庫に残り、歳入として計上可能。
実現可能性
法改正
消費税法第7条(輸出還付税)を廃止、または修正すれば可能。
国際ルールとの整合性
WTO協定やVAT(付加価値税)の国際慣行では輸出品への非課税と還付が標準。ただし、還付を廃止したとしても「違法」とはならず、国内政策の自由度に依存する。
財源シミュレーション
- 消費税廃止による歳入減:-23兆円
- 法人税増税による歳入増:+12兆円(楽観的に見積もって)
- 輸出還付金廃止による歳入増:+5兆円
- 合計 -23兆円 + 12兆円 + 5兆円 = −6兆円
上記のように、単純計算でも約6兆円の不足が生じる。法人税収が予想以上に伸びれば、例えば15兆円増ならトータルで賄える。
消費税廃止の実現可能性
理論的には可能
法人税を40%に戻し、輸出還付金を廃止すれば、消費税廃止分の大部分(約17兆円)を補える。
ただし、残りの不足分(6兆円)を埋めるには以下の策が必要。
- 国際発行(財政出動)
- 所得税増税(累進課税強化)
- 歳出削減(防衛費削減)
- 資産税導入
誰かの身を切る必要のない、「国際発行+歳出削減」で不足分は賄えばいいのではなかろうか。
消費税廃止への課題
輸出産業の反発
トヨタや日立、パナソニックなどの輸出大企業は還付金がなくなるとコスト増となり、国際競争力が低下する可能性や雇用や株価への影響を受ける可能性がある。
貿易収支悪化
輸出減少で計上黒字が縮小し、円安圧力が高まる可能性がある。
経済的抵抗
大企業や経団連が猛反発し、政治的な実現は極めてハードルが高いとされる。1989年当時とは異なり、日本企業の海外依存度が高く、法人税率の引き上げへの耐性が低いとの声もある。
国際競争力
輸出還付金廃止と法人税増税のダブルパンチで企業の海外移転が加速する恐れがあるが、前述した通り、企業が海外移転する理由の第1位は「消費需要を求めて」のことで、税制を理由とするのは少数であると総務省の調査で報告されている。
財政の硬直性
国債費や社会保障費(約37兆円)が一般会計を圧迫しており、6兆円の穴を埋める余裕がないとの声もある。
代替案
段階的アプローチ
消費税を一気に廃止せず、5%に下げつつ、法人税率を35%、還付金を半減するなど段階的に調整するという案が現実的とされるが、国民の負担を考えれば消費税廃止は急務だ。
新たな財源
金融所得課税の強化(現在20%→30%)などで不足分を補う。
国債60年償還ルールの廃止
「国債の60年償還ルール」があるのは日本だけである。国債の60年償還ルールとは、建設国債や赤字国債などの通貨発行を、借り換え分を含めて60年で償還するというルールである。
もともと公共事業で建設した建築物などの耐用年数が約60年であることに由来している。これは昭和43年5月以降に確立され、国債管理政策の根幹をなしている。
他国では国債の償還期限が来ると、新たに国債を発行して借り換えをしている。これが国際標準で「60年償還ルール」などというものは世界に存在しない。つまり、このようなアホルールが存在するのは日本だけなのだ。
PB黒字化目標を破棄
国家予算には国債償還費が計上されている。財務省は「財政法4条」の教義に則って財政規律政策を実施している。
この財政法4条を廃止すれば財政出動を阻むプライマリーバランス黒字化目標も、その存在意義を失う。
そうすれば政府の赤字を増やして、みんなの黒字を増やすことができる。
結論
法人税率を1989年以前の40%に戻して、輸出還付金を廃止すれば、消費税廃止は可能か、という問いの答えは「数字上はほぼ可能」である。
上記の実施で約17兆円を補える。残りの6兆円分を国債発行などの追加策で対応すれば実現可能だ。
それでも、現実的に困難とされる理由は、企業や財務省の反発、緊縮増税派の国会議員の抵抗があるためだ。
だから消費税廃止を可能にするには、国民の強い支持と後押しが必要である。
例えば、ネットやSNSだけでなく、国民が個々の生活圏で消費税廃止の声をあげ、国民運動にしていく。もちろん選挙(投票行動)による政党、議員への圧力なども必須だ。
個人的には先陣きって消費税減税、廃止をやろうとしている気概のある政党を応援、支持するのが何よりも近道だと考える。要するに積極財政派の政党、議員に票を集めろってこと。
つまりはすべて、一票という最大の権力を持つ国民次第、あなた次第。
関連記事