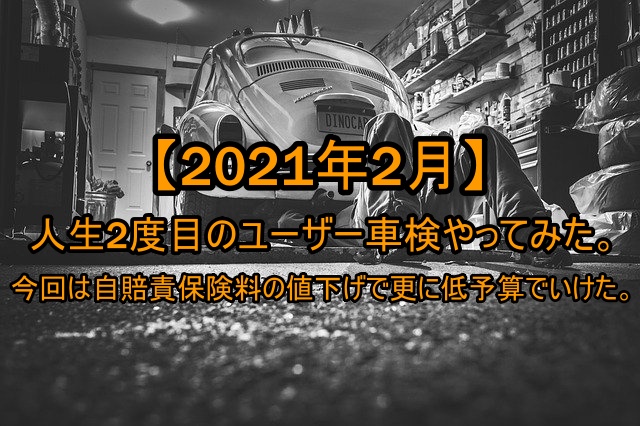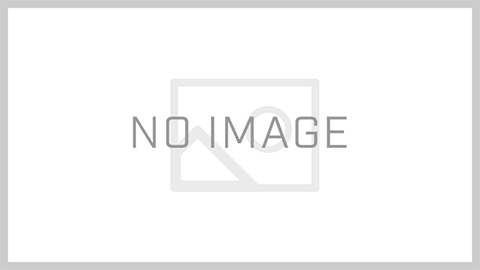財務省と増税と天下り

財務官僚が消費税増税を推進するのは大企業への還付金だったり、法人税を減税したりして大企業に恩を売り、天下り先を確保するため。
よく経団連の会長も増税を推進するよう発言しているし、財務官僚にとっても増税と天下りは二つで一つ。共存関係にあるといってもいい。
増税の見返りが「出世」や「定年後の天下り」といった成功報酬に結びついているのではないか。昨今、このような意見もよく目にするようになった。この「増税と天下り」についても少し考えてみたい。
理由
まず、財務官僚が消費税増税を推進する理由について。財務省の公式な立場としては消費税は安定財源であり、高齢化による社会保障費の増大に対応するために必要とされる。
確かに日本は少子高齢化で社会保障費が膨らんでおり、2025年度には約150兆円に達するとの試算もある。これは一般的な経済データに基づく推測だ。
消費税は広く国民全体が負担する税金で景気変動に左右されにくいため、財務省にとって「頼れる収入源」と見なされている。
しかし、近年指摘されている「大企業への補助金」や「法人税減税」が絡むと話は変わってくる。消費税には「輸出還付金」という仕組みがあり、輸出企業が支払った消費税の一部を国が還付する。
例えば、輸出品に消費税はかからない(ゼロ税率)。一方で企業が仕入れで支払った消費税は還付されるので、税率が上がれば上がるほど大企業が受け取る還付金が増えるのだ。
ところが昨今では、輸出企業が下請け企業に消費税分の値引きを強要しているケースが多く、その場合、輸出還付金は大企業への事実上の輸出補助金になっている。
つまり、輸出大企業は消費税を収めていないのに、ちゃっかり還付金だけはもらっているのではないか、と批判が集まっているのだ。
実際、輸出大企業への還付金は年間数兆円規模とも言われており、これが経団連のような団体が増税を支持する一因と考えられる。
経団連の提言でも、消費増税を「有力な選択肢」としつつ、法人税率の引き上げには慎重な姿勢を示している。
これは大企業の税負担を軽くしながら、国全体の税収を増やす手段として消費税が都合がいいからだろう。
天下り
財務官僚が退職後に大企業や関連団体に再就職することを俗に「天下り」という。
財務官僚が天下りすることは過去のデータからみても明らかだ。例えば、2010年代の調査では財務省出身者が大手銀行や企業で役員や顧問として再雇用されるケースが多数報告されている。
まず、天下り先を確保するには大企業が潤う状況を作っておくことが重要だ。消費税増税で還付金が増え、法人税減税で企業の利益が守られれば、企業側も官僚を受け入れる余裕が生まれる、というシナリオは想像に難くない。
だから財務省は解体しないといけないんです。解体というと言葉が過激ですが、やっぱり特権的な地位を得て、それを利用して天下りもしているわけです。今の内閣府の事務次官、環境省の事務次官、前の復興庁の事務次官は財務省出身者なんです。
出典:高井たかし「れいわPRESS第3号(2025.03.31発行)」
経団連会長の発言
では、経団連会長の発言はどうか。経団連の正式名称は「日本経済団体連合会」といい、日本の代表的な企業や団体で構成される総合経済団体である。
この経団連の十倉雅和会長は2023年や2024年の会見で「社会保障のためには消費税増税から逃げてはいけない」と繰り返し発言している。
これは、国民全体の負担を強調するもので、裏を返せば大企業が享受する還付金や法人税減税の恩恵には触れず、一般庶民に負担を押し付ける形になっている。
経団連が法人税減税を歓迎しつつ、消費増税を求めるのは大企業の利益を最大化する戦略と一致しているとみることもできる。
増税と天下りは共存関係なのか
増税と天下りは共存関係に近いと言えるかもしれない。なぜなら、増税が進めば大企業が潤い、天下り先が増える可能性があるからだ。
つまり、増税が天下りを減らすどころか、むしろそれを支える仕組みになっていると考える方が、筋が通る。ただし、天下りが増税の直接的な目的とまでは言えないかもしれない。
あくまで財務官僚と大企業の利害が絶妙に絡み合った結果として、こうした利権構造が生まれている可能性が高い。
いうまでもなく、普通なみの官僚は、老後の物資的保障とならんで、恣意的な解任にたいする保障をも高めるような、「官僚法」を獲得しようとする。
とはいうものの、この努力には限界がある。「官職要求権」がいちじるしく発達すると、技術的な合目的性を考慮して官職を任じたり、また、野心的な後任候補者が出世するチャンスもむずかしくなる。
こうした事情や、さらにはとりわけ、社会的に下位にある被支配者に依存するよりも、むしろ同地位者に依存しようとする傾向があるために、官僚は、だいたいにおいて、「上へ」の従属をさほど苦にしないこととなりやすい。
バーデンの聖職者のあいだにみられる現時の保守的運動は、国家と「教会」とがすぐにも分離されるかもしれないという不安に端を発したのであるが、それは、「教区の主人から下僕になりさがり」たくない、という願望にあきらかにもとづいていたのである。
出典:マックス・ウェーバー著「権力と支配」
あとがき
財務官僚が増税を推進する背景には社会保障財源の確保という建前に加え、大企業への還付金や法人税減税を通じて天下り先を間接的に支える、という動機が絡んでいる可能性は否定できない。
経団連会長の発言も、大企業の利益を守る立場から増税を後押ししているように見える。増税と天下りは、お互いを補完し合う関係にあるのかもしれない。
いずれにしても、日本が30年経済成長せずに、その犠牲になっているのは庶民であり、中小零細企業なのだ。
税金って、景気が悪いときには下げる、景気がいいときには上げるっていうのが経済学の基本なんですけど、財務省と自民党はそれと真逆のことをずっとやってきました。
その理由として、税金はいったん下げたら上げられないっていうんですけど、諸外国を見れば、コロナのときに100カ国以上が消費税を下げている。
中には下げっぱなしじゃなくて、戻している国もある。景気に合わせて機動的に上げ下げしなきゃいけないのに、やってないのは職務怠慢だと思います。
出典:高井たかし「れいわPRESS第3号」