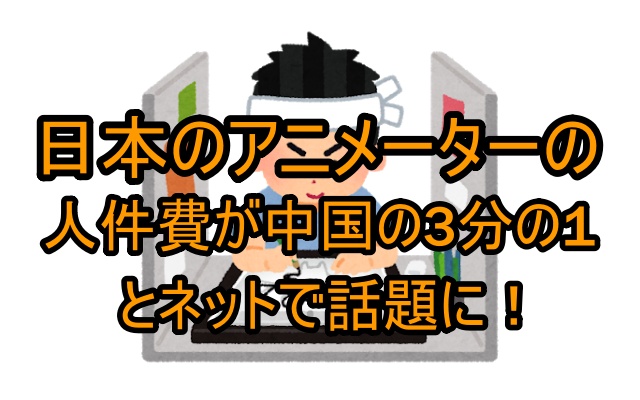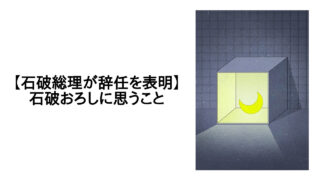【労働組合と消費税】消費税収と公務員給与の関係
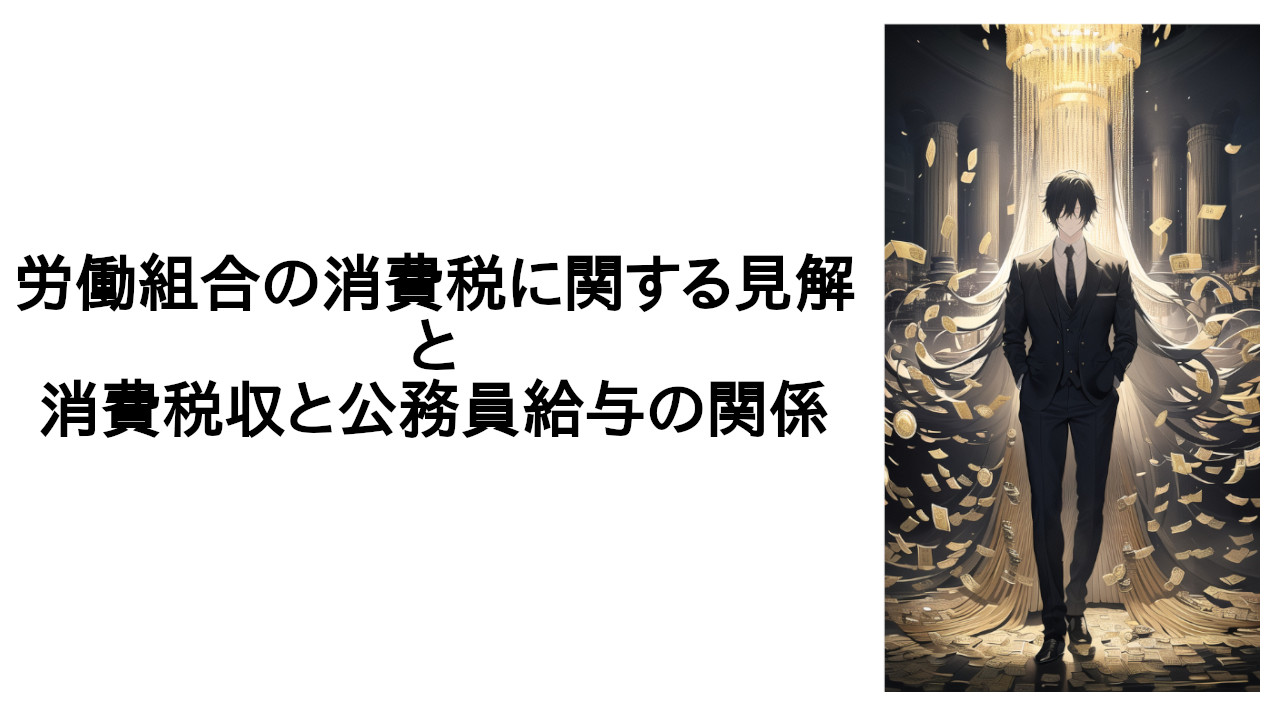
なるほど、自治労(自治体労働組合)やその他の労働組合、そして全国の公務員が消費税を自分たちの給与やボーナスの財源だと考えているフシがあるのか。
そのために消費税の減税や廃止に反対している、あるいは消極的だという話もあるのだろうか。だからこそ立憲民主党は支持母体の意向に沿い増税には積極的だが、消費税減税や廃止を頑として否定するのかな。
う〜ん確かに、消費税の一部は地方交付税として自治体に配られ、公務員の給与を含む公共サービスの資金源となっている。
この仕組みがあるために、公務員やその労働組合が消費税を維持したいと考える理由があるかもしれない。
一方で、彼らが意識的に「消費税が自分たちの給与の原資だから減税に反対している」と信じているかどうかは、やっぱり個々の意識や組合の方針によって異なってくるだろうな。
とりあえず「労働組合の消費税に関する公式見解」と「消費税と公務員給与の関係」について見ていきますか。
自治労の消費税に関する公式見解
自治労(全日本自治団体労働組合)の公式見解を示す文書で「消費税」について明確に賛成または反対を表明しているものは見当たらない。
ただし、自治労の活動方針や関連する労働運動の文脈から推測すると、いくつかのポイントが浮かび上がってくる。
自治労は公共サービスの維持・強化を重視する労働組合で、その財源として税収(消費税を含む)が重要な役割を果たしていることを認識している。
自治労の公式サイトや機関紙などでは、公共サービスの充実や労働条件の改善を求める声が強く、そのためには安定した財政基盤が必要との立場がうかがえる。
消費税が地方交付税交付金の一部として自治体に還元され、公務員の給与や公共サービスの資金源となっていることから、消費税の維持や増税に対して明確に反対を打ち出していないと見られる。
一方で、組合員の生活を圧迫する過度な増税や、消費税に依存しすぎる財政政策に対しては慎重な姿勢を示す可能性もあるのだろうか。
例えば、過去の資料では「税と社会保障の一体改革」に対する反対意見が関連組織の自治労連などで見られるが、自治労自体は連合(日本労働組合総連合会)に加盟していて、連合寄りの穏健なスタンスを取ることが多い。
公務員の給与体系と消費税収の関係
公務員の給与体系と消費税収の関係を理解するには、日本の財政構造と地方自治体の予算編成の仕組みを押さえる必要がある。
①消費税収の流れ
地方交付税は自治体の一般財源として活用され、公務員の給与を含む行政経費に充てられている。
日本では消費税の一部が地方消費税として地方自治体に配分され、さらに地方交付税交付金として自治体に還元される。
2023年度のデータによると、消費税収(国税分+地方消費税分)は約22兆円で、そのうち地方交付税交付金として約16兆円が自治体に配分されている。
②公務員の給与体系
地方公務員の給与は各自治体の条例に基づいて決定されるが、その財源は大きく分けて次のものに依存している。
- 地方税(住民税や固定資産税など)
- 国からの地方交付税
- 自治体独自の収入(使用料など)
地方交付税の原資には消費税が含まれているため、消費税収が減少すると地方交付税の額が減少し、結果として自治体の予算が圧迫される可能性がある。
これが公務員の給与や雇用条件に間接的に影響を与える構造になっている。
③消費税収と公務員給与の具体的な関係性
消費税が減税または廃止された場合、地方交付税が減額され、財源不足に陥った自治体が人件費を削減するケースが考えられる。
総務省の「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、財政再建が必要な自治体では「公務員給与のカット」や「人員削減」が実施された例(夕張市など)もある。
逆に、消費税増税によって地方交付税が増えれば、給与水準の維持や改善がしやすくなる側面もある。
④自治労の視点
自治労が消費税減税に消極的だと感じられる背景には、このような財政構造が関係している可能性がある。
組合員である公務員の給与や労働条件を守るためには、安定した財源が不可欠であり、消費税がその一翼を担っているからだ。
ただし、組合員自身も消費者として消費税の負担を負うため、増税による生活への影響を無視しているわけではなく、バランスを求める立場と考えられる。
れいわ新選組から出馬した「はんどう大樹さん」の講演依頼がキャンセルされた件について
『檻の中のライオン』の著者で弁護士のはんどう大樹さんは惜しくも落選となったが、今回の参院選2025に広島県選挙区かられいわ新選組の候補として出馬した。
そんな、はんどうさんだが、なんとれいわ新選組から選挙に出るとなった途端に労働組合と教職員組合からの講演依頼をキャンセルされたという。
どこの政党から出馬しようが、憲法やはんどうさんの講演内容に変化はない。これは一体どういうことなのだろうか。ここから次のようなことが推測できるかもしれない。
労働組合は立憲民主党を支持している
教職員組合や労働組合(自治労など)が立憲民主党を支持する傾向や立場にあるのは公然の事実である。
れいわ新選組が「消費税廃止・減税」という政策を掲げているため
また、れいわ新選組の政策である「消費税廃止・減税」が、これら組合の立場や方針と対立する可能性も考えられる。
キャンセルの動機は政治的立場か?
消費税は地方財源の一部であり、消費税減税や廃止が実現すれば、地方自治体の財源が減少し、給与や行政サービスに影響が出る可能性がある。そのため労働組合が「れいわ新選組」の候補者に対して慎重な態度を取る動機になりえる。
だが、地方財源の原資は消費税だけではない。そのため、はんどう大樹さんの講演キャンセルの直接的な動機が「消費税と公務員給与の問題」なのかどうかは公式の情報が不足しているため断定はできない。
ただし、労働組合が立憲民主党の支持母体であることや「消費税廃止・減税」という政策が地方財源に影響を与えることを懸念する政治的立場が間接的に講演キャンセルの背景にある可能性は否めない。
地方には通貨発行権がないが、国にはある
自治労の公式見解には、消費税にハッキリと賛成、反対する旨の公式な声明は見当たらないが、公共サービスと労働条件の維持を重視する立場から、消費税を含む税収の重要性を暗に認めていると解釈できる。
給与体系と消費税収の関係については、消費税は地方交付税を通じて自治体の財源となり、公務員給与の原資に間接的に影響する。
消費税の減税や廃止は彼らの給与削減リスクを高め、増税は安定性を支える可能性がある。
だからこそ、だからこその積極財政である。地方に通貨発行権はないが、国にはある。消費税廃止による地方税収の不足分は国が出せばいい。
儲かっている企業から、それなりに法人税を負担してもらう。累進課税の強化。これをやる。金融所得への課税。これもやればいいだろう。そもそも、消費税が導入されてから企業が収めるはずの法人税は年々、減税されてきた。
つまり、消費税は法人税減税のための原資ともいえる。だから、経団連に名を連ねる大企業などは消費増税に何もいわない。いわないどころか彼らのコメントからは推進しているようにしか見えない。やればやるほど社会経済が破壊されていく増税に大賛成なのだ。
消費税を廃止して、おかしな税制を本来あるべき姿(消費税が導入される前の状態)に戻す。それまでの期間の財源は国際発行で賄いながら、法人税の累進課税を強化する法整備を進めていく。
これが、消費税廃止に「国債発行」と「税(法人税累進課税強化、金融所得課税など)」の2つの財源を用いる積極財政派の主張である。
関連商品