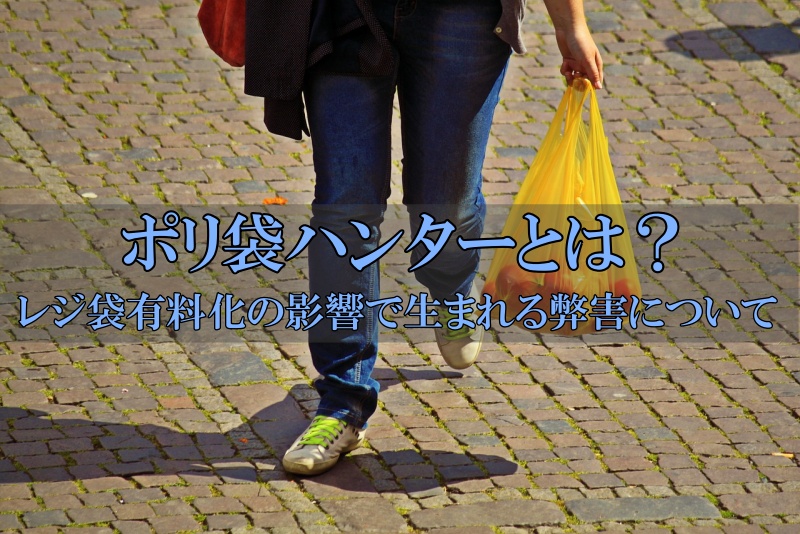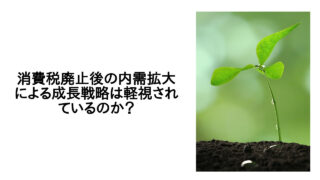財務省が消費税廃止を妨害する最大の理由
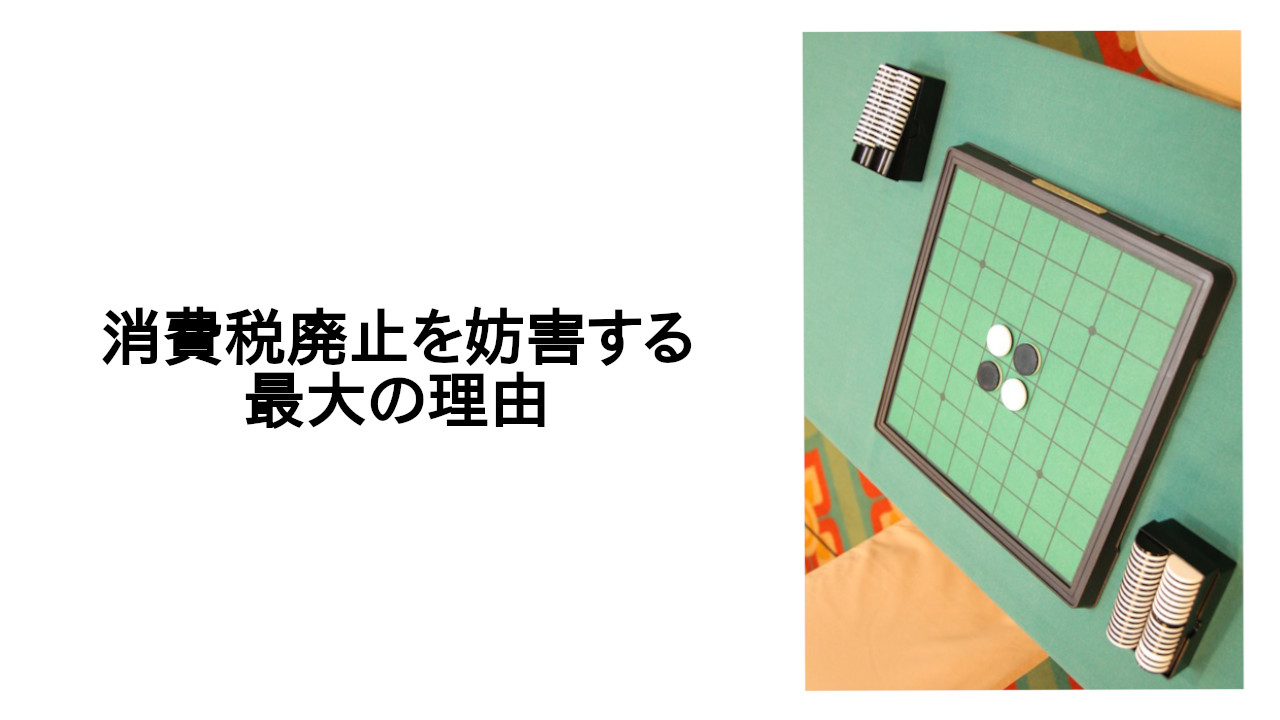
彼らが消費税廃止を妨害する最大の理由は、消費税廃止によって日本経済が再生、復活してしまったら困るから。
つまり30年間、国民を騙して搾取してきたことがバレるのを恐れているからだ、というような論調もネット上ではチラホラ見られる。
このような視点は陰謀論的なニュアンスも含む一方で、「財務省の動機」や「行動原理」を深く掘り下げる良いきっかけにもなるだろう。
財務省が消費税廃止に反対する表向きの理由
財務省の公式な立場は、「財政健全化」と「社会保障財源の確保」である。そして、以下のような表向きのロジックが財務省の資料や国会答弁で繰り返されている。
財政健全化
国債残高が約1200兆円に達し、金利上昇リスクを抑えるため、消費税のような安定財源が必要である。
社会保障
社会保障関連費は高齢化で2024年度は約35兆円に膨張。諸費税収23兆円が無くなれば、年金や医療、介護が崩壊する。
経済安定
消費税廃止で国債依存が進めば、市場の信任が揺らぎ、円安やインフレが国民生活を直撃する恐れがある。
それでも財務省は国債はこれ以上発行できない、日本は財政破綻寸前と言います。が、これもデマです。なぜそんなことを言うかというと、財務省という役所の目的が「財政健全化」なんです。それと、予算を配ってる立場だから、予算額がどんどん増えると配るおいしさがなくなる。
出典:高井たかし「れいわPRESS第3号(3月31日発行)」
財政健全化を、国民から税金や社会保険料を取るための言い訳として手放したくないんじゃないかと思うほどですよね。でも介護保険なんて典型ですが、保険料を払っているのにサービスは減るわ自己負担は増えるわで、国の保険詐欺みたいな状況です。
出典:くしぶち万里「れいわPRESS第3号(3月31日発行)」
「経済が再生したら困る」や「国民を騙してきたことがバレたら困る」という見方
このような見解は、財務省の動機を「権力維持」や「自己保身」に求めるもので、次のように解釈できる。
財務省の権力と消費税
予算を支配
財務省は「予算編成権」というある種の権力を使って全省庁を統制し、事実上、日本の政策を支配している。
消費税は一般会計の約三分の一(23兆円)を占める基幹財源とされ、これを失うと歳出削減や増税を他省庁に強いらざるを得なくなり、権限が弱まる可能性がある。
失われた30年の物語
1989年の消費税導入以来、「財政再建」や「社会保障のため」と国民に訴えてきた。
もし、消費税を廃止して経済が再生(復活)し、その不足分を国債発行で賄っても何の問題もないと証明されれば、「この30年間の緊縮財政は何だったのか?」と批判が噴出することは免れない。
経済再生への恐怖
緊縮の正当性
1990年代以降、1997年に消費税増税に踏み切った橋本政権や小泉政権で緊縮財政を推進し、「失われた30年」といわれる経済停滞を招いたという批判がある。
だから、消費税廃止で内需が拡大し、経済成長すれば「緊縮政策が日本の成長を阻害していた」と国民にバレる可能性がある。
自己保身
財務官僚のキャリアは「財政健全化の実績」で評価される。
消費税を廃止して経済が好転すると「財務省の政策が間違っていた」と責任追及され、出世が遠のくだけでなくメンツが傷つく恐れがある。
それどころか最近のネット世論の盛り上がりを見ていると、権力の一極集中を分散するため、財務省が「歳入庁・歳出庁・国税庁」に分割され、財務省自体が無くなる可能性もある。
「国民を騙してきた」ことの根拠
使途の不透明性
消費税は当初「一般財源」だったが、2012年の「社会保障・税一体改革」で、これからは「社会保障に充てる」と説明された。
しかし、一般会計内で防衛費や国債利払い、法人税減税、輸出還付金にも使われており、「消費税は全額、福祉のために使われている」と思い込んでいた国民との約束を反故にした。
一体改革には慎重でした。デフレ下に加え、震災の影響を受けている時に消費税を上げるべきではない。一体改革は、税金を上げて社会保障に回すのではなく、むしろ借金の返済に充てるのが狙いでした。政局的に見ても、自民党が政権を取り戻す上で、民主党が掲げた増税と真っ向から勝負すべきではないかと思っていました。
(中略)
社会保障と税の一体改革は、財務省が描いたものです。当時は、永田町が財務省一色でしたね。財務省の力は大したものですよ。時の政権に、核となる政策がないと、財務省が近づいてきて、政権もどっぷりと頼ってしまう。
菅直人首相は、消費増税をして景気を良くする、といった訳の分からない論理を展開しました。民主党政権は、あえて痛みを伴う政策を主張することが、格好いいと酔いしれていた。財務官僚の注射がそれだけ効いていたということです。
出典:安倍晋三著「安倍晋三回顧録」
増税の効果が疑問視される
消費税が、「3%→5%→8%→10%」と上がった30年でGDP成長は低迷。消費税が増税されるたびにリーマンショック級の経済不況が日本を襲った。
1990年に約430兆円だったGDPが2023年には約600兆円と名目で1.4倍程度にしか増えていない。「増税すれば良くなるという約束がすこしも果たされていない」と国民は不信感が募るいっぽうなのだ。
事実と推測
事実
財務省は消費税廃止に強く反対し、「財政危機」と「社会保障崩壊」を強調する。
消費税導入後、経済は低迷し、国債残高は増大(1990年:約200兆円→2025年:約1200兆)。
税収は2024年度で過去最高の73.4兆円だが、歳出超過で赤字は解消せず。
推測
「経済再生への抵抗なのではないか」という憶測が飛び交う一方、財務省が意図的に成長を阻害しているという証拠はない。
だが、彼らのおこなう緊縮政策が経済を冷やし続けたことは一部の政治家や元官僚、経済学者、評論家などが指摘している。
国民への欺瞞
「財政健全化のため」と言いながら増税し、国民のための歳出は削減するが、防衛費増額には柔軟な姿勢を示す矛盾。このような態度から国民より省益を優先していると見られても仕方ないだろう。
この見方を裏付ける声
SNSでの反応
SNSでは以下のような声が散見される。
- 財務省は消費税で国民を搾取し、大企業と自分たちの権力を守っているだけ
- 消費税を廃止したら、経済が回ることがバレるから阻止しようと必死
学者の視点
MMT支持者や反緊縮派の学者たちは「財務省は国債リスクを誇張し、国民を脅してきた」と批判。また消費税廃止で経済が再生すれば、その論理が崩れると主張している。
財務省が消費税廃止を阻む最大の理由は何なのか?
- 経済が再生したら困る
- 騙してきたことがバレるのを恐れている
といったことが、その理由かどうかは内部文書や内部告発といった証言がない限り推測の域を出ない。しかし、可能性としては次のことが考えられる。
過去の正当化
30年間の緊縮路線が「誤りだった」と認めざるを得なくなるシナリオを恐れている。
コントロールの喪失
消費税廃止による内需拡大で経済が自立し国債依存が許容されれば、今後、財務省の「財政危機」というカードが効かなくなる。つまり、彼らは権力、支配力を失う。
その一方で財務官僚が純粋に「財政破綻を防ぎたい」と考えている可能性も否定できないという意見もある。
だが、そもそも消費税というものが「直間比率の是正」から始まったことを考えれば、その可能性は限りなく低くなる。
景気に左右されない「安定財源」を見つけた彼らは直間比率が是正されたあとも、その甘い果実を手放そうとせず、その理由や目的をあとから付け替えながら今日までこの国家弱体化装置を稼働し続けてきた。
結論
「財務省は経済再生を恐れている」とまでは断言できないが、彼らが消費税に固執する背景には「財政健全化という物語をなんとしても守りぬかなければならない」という意図があるのは確かだ。
彼らは、失われた30年の原因が消費税や緊縮政策のせいだと認めようとしないだろうが、「騙されていたのでは?」という国民の不信感が募るのも理解できる。
もし、消費税を廃止して経済が回りだし、日本が復活を遂げるようなことになれば財務省の権威は失墜するだろう。
それこそ最近、大きな話題にもなっている「財務省解体」なんて話も途端に現実味を帯びてくる。
どうせ守るんなら、そんなカルトの教義のような物語ではなく、多くの国民の生活の方を守ってもらいたいね。